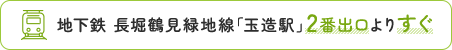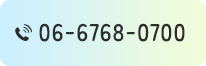肝硬変の症状|初期・中期・末期ごとのサインと進行例【専門医監修】
肝硬変は初期の自覚症状が少なく、進行すると命に関わるリスクもあります。本ページでは、肝硬変の初期・中期・末期に現れる症状と、その進行パターンについて専門医がわかりやすく解説します。また、早期発見に役立つ「セルフチェックリスト」や、進行パターンのイメージ図もご紹介します。心配な症状がある方は、ぜひ参考にしてください。
- 肝硬変とは?
- 肝硬変の初期症状|セルフチェックリスト
- 肝硬変の中期症状と注意点
- 肝硬変の末期症状|危険なサインとは
- 肝硬変の進行と症状のステップ解説
- 肝硬変の最も多い原因は?
- 当院で行う肝硬変の検査
- 肝硬変の治療
- よくある質問(FAQ)
肝硬変とは?
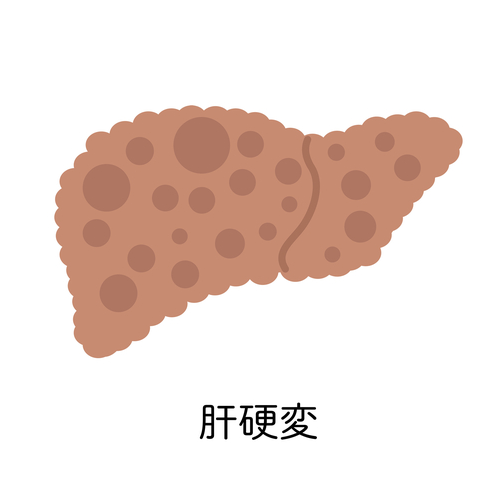 肝硬変は、肝臓の細胞が破壊と再生を繰り返す中で、肝臓全体が硬く小さくなり、正常な機能を失っていく病気です。
肝硬変は、肝臓の細胞が破壊と再生を繰り返す中で、肝臓全体が硬く小さくなり、正常な機能を失っていく病気です。
初期段階ではほとんど自覚症状がないことが特徴ですが、進行すると疲れやすさ、食欲低下、むくみなどの体のサインが現れ、さらに悪化すると黄疸、腹水、意識障害といった深刻な症状へとつながります。肝硬変の主な原因には、過剰な飲酒、暴飲暴食、B型・C型肝炎ウイルス感染、非アルコール性脂肪肝(NASH)などがあります。これらにより慢性的に肝臓が傷つくと、肝臓内にコラーゲンといったたんぱく質が蓄積し、「線維化」と呼ばれる硬化が進行します。
この線維化が進むと、肝臓の柔軟性は失われ、機能も低下していきます。最終的に肝臓全体が硬く小さくなると「肝硬変」となり、放置すれば肝不全や肝がんといった命に関わる合併症に至ることもあります。
肝硬変の進行を防ぐには、早期に気づき、適切な治療を開始することが何より重要です。
肝硬変の初期症状|セルフチェックリスト
以下のような症状に心当たりがある場合は、肝硬変の初期段階かもしれません。
- 最近、疲れやすさを感じるようになった
- 食欲が落ち、すぐに満腹になる
- 体重が意図せず減少している
- 足や足首にむくみが出る
- 皮膚がかゆくなることがある
- 手のひらが赤くなる(肝掌)
- 夜間にこむら返り(足がつる)を起こすことが増えた
2つ以上当てはまる場合は、念のため医療機関で検査を受けることをおすすめします。
肝硬変の中期症状と注意点
病気が進行すると、より明らかな症状が現れ始めます。
- 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)
- お腹が張り、腹水が溜まる
- 吐き気や消化不良が頻発する
- 集中力が低下し、軽度の意識混濁が見られる(肝性脳症)
- あざができやすく、出血が止まりにくい
これらの症状が見られる場合は、肝機能の低下が進んでいる可能性が高く、早急な対応が必要です。
肝硬変の末期症状|危険なサインとは
さらに進行すると、命に関わる重篤な症状が現れます。
- 大量の吐血や黒色便(消化管出血)
- 意識障害が進み、昏睡状態に至る(末期肝性脳症)
- 腹水が大量に溜まり、呼吸が苦しくなる
- 腎機能低下により尿量が激減する(肝腎症候群)
- 感染症にかかりやすくなる(腹膜炎、敗血症など)
この段階では緊急治療が必要です。早期の受診・治療が生死を分けることになります。
肝硬変の進行と症状のステップ解説
肝硬変は、初期から末期にかけて段階的に症状が進行していきます。以下に、症状の変化をステップごとにわかりやすくまとめました。
【ステップ1】初期症状:疲れやすい・食欲不振
この段階では、疲れやすさや倦怠感、食欲の低下など、日常生活に支障が出にくい軽微な症状が現れます。
【ステップ2】中期症状:むくみ・皮膚のかゆみ
体内の水分バランスが崩れ、足や顔にむくみが生じたり、皮膚のかゆみが強くなることがあります。
【ステップ3】後期症状:黄疸・腹水・消化不良
肝機能が著しく低下し、皮膚や目が黄色くなる「黄疸」や、腹部の張り・膨満感を伴う「腹水」などが現れます。
【ステップ4】重篤症状:吐血・意識障害
食道静脈瘤の破裂による吐血や、肝性脳症による意識の混濁・混乱が見られるようになります。
【ステップ5】末期症状:多臓器不全・感染症
免疫力の低下により感染症にかかりやすくなり、腎不全や肺炎など多臓器への影響が現れることもあります。
現在のご自身の症状がどの段階にあたるかを把握することは、早期治療や生活改善のために非常に重要です。
気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。
肝硬変の最も多い原因は?
 肝硬変の最も一般的な原因は、長期間にわたる肝臓の炎症です。従来、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどの肝炎ウイルスによるものが主でした。しかし、近年は過剰なアルコール摂取や脂肪肝が急増しています。そのほか、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など様々な原因が考えられます。
肝硬変の最も一般的な原因は、長期間にわたる肝臓の炎症です。従来、B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスなどの肝炎ウイルスによるものが主でした。しかし、近年は過剰なアルコール摂取や脂肪肝が急増しています。そのほか、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など様々な原因が考えられます。
特にアルコールは肝臓病と深く関わっており、適量を超えた飲酒が続くと肝硬変に至ることもあります。自己免疫性肝炎は、免疫系が誤って自分の肝細胞を攻撃する病気で、治療が遅れると肝硬変に至ることがあります。この疾患は主に中年以降の女性に見られますが、近年では男性患者も増加しており、若年層にも発症することがあるため、注意が必要です。
当院で行う肝硬変の検査
 当院では、肝臓専門医である院長が直接行う腹部超音波検査を通じて、肝疾患を早期に発見し、正確な評価を行っています。
当院では、肝臓専門医である院長が直接行う腹部超音波検査を通じて、肝疾患を早期に発見し、正確な評価を行っています。
また、検査には最新鋭の超音波機器「ARIETTA 750 Deep Insight SE」を使用し、肝硬変の進行度を数値化して見える化することで、患者様に最適な治療方針をご提案しています。
超音波機器「ARIETTA 750 Deep Insight SE」の機能
超音波エラストグラフィーで肝硬度を測定します
「超音波エラストグラフィー」は、肝臓の硬さを測定する最新技術です。この検査では、肝硬変の進行具合を非常に正確に数値化することができ、肝臓がどれくらい硬くなっているかを視覚的に把握することができます。進行度を明確に示すことで、患者様にも理解しやすい形で治療方針をお伝えできます。
超音波減衰法検査で脂肪量を評価します
肝臓に蓄積された脂肪量も、肝疾患の進行やリスクを予測する重要な指標です。超音波減衰法(iATT)を使用することで、肝臓内の脂肪量を高精度で測定できます。この検査により、脂肪肝やその進行を早期に発見し、肝硬変のリスクを未然に防ぐための対策を講じることが可能です。
検査のメリット
 当院で行う肝硬変検査の大きなメリットは、検査結果が数値化され、進行度が視覚的に把握できる点です。これにより、患者様一人ひとりに最適な治療方法を提案できるだけでなく、治療の進行状況も客観的に評価することができます。
当院で行う肝硬変検査の大きなメリットは、検査結果が数値化され、進行度が視覚的に把握できる点です。これにより、患者様一人ひとりに最適な治療方法を提案できるだけでなく、治療の進行状況も客観的に評価することができます。
さらに超音波検査の特性上、非侵襲的であり、痛みや被ばくの心配もありません。治療の効果を確実にチェックできるため、より効果的なアプローチが可能となります。肝疾患について不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
肝硬変の治療
肝硬変の治療方法は、原因や進行度に応じて異なります。治療の目標は、肝硬変の進行をコントロールし、肝臓の機能を保つことです。
ウイルス感染による肝硬変
ウイルス感染による肝硬変の場合、ウイルスを抑える抗ウイルス薬が使用されます。早期の治療で、肝機能の進行を遅らせることが期待できます。
アルコール性肝硬変
アルコール性肝硬変の場合は、まずアルコールの摂取を避けることが最も重要です。また、生活習慣の見直しや、肝臓に負担をかけない食事を心がけることも必要です。栄養療法やサプリメントが処方されることもあります。
肝移植
肝硬変が進行し、肝臓の機能が極めて低下している場合、肝移植が必要になることがあります。肝移植は、健康なドナーから肝臓を移植し、肝機能を回復させる手術です。しかし、重症度や待機期間、費用などの要因が関わるため、すぐに行える治療法ではありません。そのため、早期発見と適切な治療が重要です。
薬物療法
症状に応じて使用される薬剤は異なりますが、大きく分けると次のようなものがあります。
肝庇護剤
肝臓の炎症を抑え、進行を遅らせます。
利尿剤
腹水やむくみを軽減します。
胃腸粘膜保護薬
胃腸の粘膜を保護し、静脈瘤の破裂を防ぎます。
難吸収性抗生物質
主に腸管内に作用し、高アンモニア血症を改善します。
BCAA製剤
不足しているアミノ酸を補います。
これらの薬は、患者様の状態に合わせて処方され、進行を遅らせたり症状を改善したりする効果が期待できます。
生活習慣の見直し
肝硬変の進行を防ぐためには、生活習慣の見直しが重要です。具体的には、以下のことが挙げられます。
病状に合った食事
肝臓に優しい食事を心がけましょう。
禁酒
肝臓への負担を軽減するために、アルコールは完全に避けましょう。
ストレスのコントロール
ストレスが肝臓に悪影響を与えるため、リラックスできる時間を大切にしましょう。
特に、胃腸に負担をかける食事や生の食べ物は避けるようにし、軽い運動や趣味を楽しむことも有効です。
肝硬変の食事療法
患者様の病状に応じた食事療法が大切です。以下は、代償性肝硬変と非代償性肝硬変の場合に分けた食事のポイントです。
代償性肝硬変の
食事のポイント
肝機能低下に対応するため、以下のポイントを意識しましょう。
- カロリー、たんぱく質は適量を心がける。
- ビタミン、ミネラル、食物繊維をきちんと摂取する。
- 塩分、鉄分は摂りすぎないよう注意。
バランスの良い食事を心がけ、便秘を防ぐために野菜や海藻を積極的に取り入れましょう。
非代償性肝硬変の
食事のポイント
病状に応じた食事管理が必要です。
- 腹水・むくみがある場合:塩分と水分の摂取を控えめに。
- 食道静脈瘤がある場合:刺激物や硬い食物を避け、よく咀嚼。
- 糖尿病を合併している場合:一度に大量に食べず、砂糖や果物の摂取を控える。
- 肝性脳症がある場合:タンパク質の摂取を控え、食物繊維を多く摂る。
食事は適量を守ることが基本です。
よくある質問(FAQ)
肝硬変の症状に関して、患者様からよくいただくご質問をまとめました。
疲れやすさだけでも肝硬変の可能性はありますか?
はい。肝硬変の初期では疲れやすさが唯一のサインとなることもあります。他の症状がない場合でも、念のため検査を受けることをおすすめします。
むくみが続いています。肝臓の異常でしょうか?
足や足首のむくみは、肝臓の機能低下によって引き起こされることがあります。特に他の症状も伴う場合は、医師に相談してください。
症状がなくても肝硬変が進行していることはありますか?
あります。肝硬変は初期では無症状の場合も多いため、健診や血液検査での早期発見が重要です。