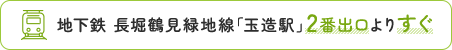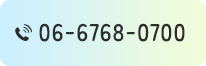アルコール性肝障害とは?
 アルコール性肝障害は、長期間にわたる過剰なアルコール摂取によって引き起こされる
アルコール性肝障害は、長期間にわたる過剰なアルコール摂取によって引き起こされる
病気です。アルコールが体内に入ると、肝臓で分解される過程で有害物質「アセトアルデヒド」が生成されます。通常、肝臓はこのアセトアルデヒドを無害な物質に代謝しますが、大量飲酒が続くと、アルコールを分解する酵素が過剰に働き続けることで肝臓の機能が低下し、やがてアセトアルデヒドを適切に分解できなくなります。
その結果、肝臓の細胞に持続的な変化が生じ、肝細胞の変性・壊死と線維化が進行します。また、炎症や脂肪の蓄積も起こり、肝臓の機能は徐々に衰えていきます。この状態が進行すると、最終的には肝硬変や肝がんといった重篤な病気へと発展する可能性があります。
特に注意が必要なのは、アルコールへの反応には個人差があるという点です。遺伝的に分解酵素が少ない方や、ホルモンの影響でアルコールの代謝速度が遅い女性は、男性に比べてアルコール性肝障害のリスクが高くなります。そのため、自身の体質や性別に応じた適切な飲酒量を守ることが重要です。
アルコール性肝障害の重症度
アルコール性肝障害は、次のような段階を経て進行していきます。
アルコール性脂肪肝:
(軽症)
原因
過度の飲酒により、肝臓でのアルコール代謝が追いつかなくなり、中性脂肪が肝臓に蓄積することが大きな要因となります。
症状
初期段階では自覚症状はほとんどありませんが、肝臓が腫れることで右上腹部に違和感を感じることがあります。また、疲労感や食欲が落ちるといった症状が現れることもあります。
治療
この段階では、禁酒または節酒することで肝臓の状態は概ね回復可能です。これに加えて、バランスの良い食事と適度な運動を心がけることで、より確実な回復が期待できます。
アルコール性肝炎:
(中等度)
原因
脂肪肝の状態でさらに飲酒を続けると、アルコールの分解過程で生じるアセトアルデヒドにより肝細胞が持続的に傷つけられ、肝臓に炎症が起こります。
症状
この状態でも無症状の方も多くおられます。また、強い疲れを感じたり、食欲が無くなったり、吐き気や嘔吐が起こることもあります。血液検査では肝機能の異常が確認されます。
治療
この段階では完全な禁酒が必須となり、肝臓を保護する薬の服用が必要です。十分な栄養摂取と休養も大切で、症状が重い場合は入院治療が必要となることもあります。
肝硬変:(重度)
原因
長期の飲酒により肝細胞の破壊と再生が繰り返された結果、肝臓が硬く変化して線維化した状態です。アルコール性肝炎の治療を行わずに放置し続けることで進行します。
症状
おなかに水がたまる(腹水)、食道静脈瘤、黄疸の悪化、意識障害(肝性脳症)といった深刻な症状が現れます。また、全身のだるさやむくみ、出血しやすくなるなどの症状も現れます。
治療
この段階では、永久的な禁酒が絶対条件となります。合併症に対する治療や、低塩食を中心とした食事療法、利尿薬などの薬物療法が必要です。症状が重症な場合は肝臓移植が検討されます。また、定期的な検査と経過観察が欠かせません。
アルコール性肝障害は、早期発見・早期治療が何より重要です。特に、禁酒による進行防止が最も効果的な治療法となりますので、症状が軽いうちから適切な対応を心がけましょう。
アルコール性肝障害の診断方法
アルコール性肝障害の診断は、患者さまのアルコール摂取歴、症状、そして各種検査結果を総合的に判断して行います。
飲酒歴の確認
アルコール性肝障害の診断では、まず詳細な問診から始まります。医師は患者さんの飲酒歴、具体的な飲酒量、飲酒パターンについて丁寧に聴取します。この際、純エタノールに換算した1日の平均摂取量を評価することが重要です。一般的に、1日平均純エタノール60g以上の常習的な飲酒が続くと、アルコール性肝障害のリスクが高まります。
飲酒量の目安
-
ビール中瓶(500ml)1本:20g
-
日本酒1合:21.5g
-
ワイン(12%、120ml):24g
-
ウイスキーダブル水割り1杯:20g など
※女性は男性に比べ、より少ない飲酒量でも、短期間の飲酒でも重度の肝障害になりやすいことが報告されています。
血液検査
検査の中心となるのは血液検査です。肝細胞の障害を示すASTやALT、アルコールによる肝障害で上昇しやすいγ-GTP、胆道系の状態を反映するALPなどを測定します。また、肝臓の合成能を示す血清アルブミン値や、肝硬変の進行度を反映する血小板数なども重要な指標となります。
画像検査
肝臓の状態を確認するために、超音波検査を行います。これにより、肝臓の大きさや質感の変化、脂肪肝や肝硬変の兆候を把握できます。また、当院ではエラストグラフィーと呼ばれる検査で、肝臓の硬さを測定し、肝硬変の進行具合を評価することも可能です。
必要に応じてCTやMRI検査を行い、より詳細な肝臓の状態を把握します。CTでは肝臓の形態異常や脂肪沈着の程度、MRIではさらに詳細な組織の状態を評価できます。
アルコール性肝障害の禁酒期間
アルコール性肝障害の進行具合によって、禁酒を続ける期間が異なります。
肝臓は禁酒によって回復することが期待できますが、その回復には時間がかかる場合があります。以下に、各段階における禁酒期間の目安をご紹介いたします。
軽度のアルコール性肝障害(脂肪肝)
禁酒期間:1〜2ヶ月程度
脂肪肝のような軽度の肝障害の場合、禁酒を続けることで肝臓の機能が改善し、脂肪が減ることが多いです。この段階では、比較的早く回復が見られることがよくあります。1ヶ月から2ヶ月の禁酒で改善が期待できますが、回復後もアルコールを再び摂取すると肝臓に負担をかけてしまうため、継続的な禁酒が大切です。
中等度のアルコール性肝障害(アルコール性肝炎)
禁酒期間:数ヶ月〜半年以上
アルコール性肝炎が進行している場合、禁酒を続けることで肝臓の炎症が落ち着き、肝機能が改善します。この段階では、数ヶ月から半年以上の禁酒が必要になることが多いです。回復には時間がかかることがありますが、症状によっては早く改善することもあります。ただし、完全に治るには長期間の禁酒だけでなく、治療や生活習慣の見直しも重要です。
重度のアルコール性肝障害(肝硬変)
禁酒期間:完治するまで
一生続ける必要があります
肝硬変の段階に進んでしまうと、肝臓の損傷が永久的になっているため、完全に回復することは難しくなります。しかし、禁酒を続けることで、肝硬変の進行を遅らせたり、合併症を予防したりすることができます。肝硬変を患っている場合、飲酒を続けることは非常に危険で、生命にかかわることもあります。ですので、禁酒は生涯にわたって続けることが必要です。
アルコール性肝障害は治る?
治療方法
当院では、アルコール性肝障害の治療において、患者さま一人ひとりの状態に合わせて、最適な治療をご提案しています。アルコール性肝障害は、過度のアルコール摂取が原因で肝臓にダメージを与える病気ですが、早期に適切な治療を受けることで、肝機能の回復が期待できます。
禁酒のサポート
 アルコール性肝障害の治療において最も大切なのは「禁酒」です。アルコールを摂取し続けると、肝臓のダメージはどんどん進行してしまいますが、禁酒を続けることで、炎症が収まり、脂肪の蓄積も改善されることがあります。当院では、禁酒を続けやすくするために、カウンセリングやモチベーション維持のサポートを行っています。患者さまが禁酒を無理なく続けられるように、心身のケアも大切にしています。
アルコール性肝障害の治療において最も大切なのは「禁酒」です。アルコールを摂取し続けると、肝臓のダメージはどんどん進行してしまいますが、禁酒を続けることで、炎症が収まり、脂肪の蓄積も改善されることがあります。当院では、禁酒を続けやすくするために、カウンセリングやモチベーション維持のサポートを行っています。患者さまが禁酒を無理なく続けられるように、心身のケアも大切にしています。
肝機能改善のための
薬物療法
アルコール性肝障害が進行している場合、薬物治療が必要となることがあります。抗炎症薬や肝臓を保護する薬を使い、肝機能の回復をサポートします。また、肝臓に負担をかけず、生活習慣を整えることも重要です。栄養士による食事指導や、適度な運動を取り入れた治療を行い、肝臓を元気に保つお手伝いをさせて頂きます。
生活習慣の改善
禁酒だけでなく、健康的な生活習慣を維持することが、肝臓の回復には欠かせません。当院では、食事内容の見直しや運動習慣のアドバイスを行い、肝臓にやさしい生活をサポートします。特に脂肪肝や肝炎の段階では、食事管理が回復を早めるため、個別に栄養指導を行い、患者さまのペースに合わせた生活改善を支援いたします。
定期的な検査と経過観察
アルコール性肝障害の進行を防ぐためには、定期的な検査と経過観察が大切です。肝臓の状態を確認するために、血液検査や画像検査を定期的に行い、治療が効果を上げているかを確認します。その上で、必要に応じて治療計画を見直し、最適な方法でサポートを続けます。