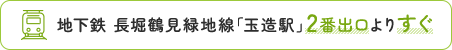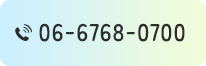- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 睡眠時無呼吸症候群セルフチェック
- 睡眠時無呼吸症候群はどうして危険なの?
- 睡眠時無呼吸症候群の原因
- 睡眠時無呼吸症候群の検査
- 睡眠時無呼吸症候群の治療
- 睡眠時無呼吸症候群に関するよくある質問
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
 睡眠時無呼吸症候群とは、大きないびきとともに、睡眠中に繰り返し呼吸が止まる疾患です。医学的な定義によれば、10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が弱くなる「低呼吸」が、1時間に5回以上続く状態を指します。睡眠中に無呼吸が起こると、体が低酸素の状態に陥ります。この低酸素状態が毎晩継続し、年単位で続けば、心臓・血管系の疾患や多くの生活習慣病のリスクが高くなります。
睡眠時無呼吸症候群とは、大きないびきとともに、睡眠中に繰り返し呼吸が止まる疾患です。医学的な定義によれば、10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や、呼吸が弱くなる「低呼吸」が、1時間に5回以上続く状態を指します。睡眠中に無呼吸が起こると、体が低酸素の状態に陥ります。この低酸素状態が毎晩継続し、年単位で続けば、心臓・血管系の疾患や多くの生活習慣病のリスクが高くなります。
高血圧との関連は昔からよく分かっており、狭心症や心筋梗塞、脳卒中の発症にも繋がります。低酸素状態になると、脳が守るために目を覚まし、呼吸が再開します。
この状態が続くと深い眠りになれず、睡眠不足に陥ります。その結果、「昼間の強い眠気」「倦怠感」「朝起きる時の頭痛」「気分の沈み」などが現れ、仕事や勉強の進捗が悪くなることもあります。
交通事故の調査によると、事故率が約2.6倍にも上昇するとされています。このように、SASは日常生活に支障をきたし、健康障害だけでなく、公共の安全性にも影響を及ぼす疾患だと分かります。
睡眠時無呼吸症候群
セルフチェック
以下の質問に該当するものがいくつあるか、ご確認ください。

- 日中に強い眠気を感じることがある
- いびきをかくと言われたことがある
- いびきが途中で止まると指摘されたことがある
- 睡眠中に息苦しさや窒息感を覚えることがある
- 朝起きたときに口が渇いている
- 朝起きたときに頭痛を感じることがある
- 十分に寝たはずなのに疲労感が残る
- 夜間にトイレに行くことが多い
- 肥満傾向がある(BMIが25以上)
- 高血圧や心疾患を指摘されたことがある
チェック結果の確認
- 該当が0〜2項目の場合
現時点でのリスクは低い可能性がありますが、いびきや日中の眠気がある場合は注意が必要です。 - 該当が3〜5項目の場合
睡眠時無呼吸症候群の可能性があるため、ご相談ください。 - 該当が6項目以上の場合
睡眠時無呼吸症候群のリスクが高い可能性があります。一度、検査をご検討ください。
睡眠時無呼吸症候群は
どうして危険なの?
睡眠時無呼吸症候群が引き起こすリスクについて、少し詳しく見ていきましょう。
心血管疾患
無呼吸や低呼吸が毎晩繰り返されると、体内の酸素供給が不足し、心臓がその不足を補おうと過剰に働きます。この負担が心臓や血管にかかり、やがて心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まる可能性があります。また、呼吸が止まるたびに目が覚めることで自律神経のバランスが崩れ、昼間に交感神経が過剰に刺激され、血圧が上昇してしまいます。このような影響が積み重なることで、血管が弱くなり、狭くなることもあります。
こうした問題は初期の段階では気づきにくいことが多いため、知らないうちに進行してしまうことがあります。無理なく治療を受けることで、健康リスクを大きく減らすことができます。
生活習慣病
自律神経やホルモンバランスが崩れ、食欲を抑える「レプチン」が減少し、食欲を増進させる「グレリン」が増えてしまいます。その結果、食事量が増えてしまい、太りやすくなることがあります。肥満になると、インスリンの働きが悪化し、血糖値が上昇しやすくなります。これが原因で、糖尿病になりやすくなるのです。
すでに糖尿病を抱えている場合、症状の悪化を防ぐためにも、生活習慣の見直しが重要です。特に肥満を気にされている方は、睡眠時無呼吸症候群の予防や改善に向けて、食事や生活を見直すことが望ましいです。
仕事や学習への影響
無呼吸や低呼吸が原因で、毎晩のように睡眠が妨げられることがあります。その結果、十分な眠りをとることができず、朝起きた後にもなかなか眠れず、睡眠の質が著しく低下します。
この影響で、昼間に眠くなり、仕事や勉強に集中できなくなり、通常なら起こりえないミスをしてしまう恐れがあります。
特に深刻なのは、居眠り運転や労災事故によって命を落としたり、他人に危害を及ぼしたりするリスクがあることです。昼間の眠気に悩んでいる方は、過労や年齢だけでなく、睡眠時無呼吸症候群にかかっている可能性も考慮に入れてみてください。
精神疾患との関係
睡眠時無呼吸症候群は、うつ病の発症リスクを高めるとも言われています。実際、うつ病と診断された方の中には、睡眠時無呼吸症候群が原因で似たような症状に悩んでいたケースもあります。睡眠不足が続くと、イライラしたり、興味が減退したりと、うつ病に似た症状が現れることがあります。ですが、睡眠時無呼吸症候群を適切に治療すると、睡眠の質が改善され、それによって症状が楽になることも期待できます。精神的な症状があった場合は、睡眠時無呼吸症候群の治療を検討してみるのも一つの手です。
また、精神疾患の治療中に睡眠薬を使用されている方もいらっしゃいますが、睡眠薬が逆に睡眠時無呼吸症候群の症状を悪化させることもあります。そのため、治療の際には医師とよく相談することが大切です。
生存率について
睡眠時無呼吸症候群に関する調査によると、治療を受けなかった重症患者の8年後の生存率は63%という結果が出ています。一方、UPPP手術のみを受けた患者さんの生存率は重症患者とほぼ変わりませんが、CPAP治療を受けた患者さんでは死亡例は報告されていません。
無呼吸そのものが直接的な死因となることはほとんどありませんが、長期的な心血管疾患や生活習慣病のリスクが高まることは確かです。しかし、適切な治療を受けることで、生存率が健康な方と同じか、それ以上に改善される可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群の原因
①閉塞性睡眠時無呼吸
呼吸は、空気を鼻や口から吸い込んで喉を通し、肺に届けることで酸素を取り入れ、二酸化炭素を体外に排出する仕組みです。しかし、この空気の流れが何らかの原因で妨げられると、呼吸が困難になり、無呼吸症状が現れます。呼吸を妨げる原因は次のようなものがあります。
- 首や喉周りに脂肪が多い
- 扁桃腺(口蓋扁桃、舌扁桃、咽頭扁桃など)が大きい
- 口が小さい
- 舌根部が肥大している
- 口蓋垂(のどちんこ)が膨らんでいる
肥満など後天的な要因は、体重の減少などで改善が可能です。ただし、骨格的な要因も影響しているため、正確な原因を特定することが治療にはとても重要です。
②中枢性睡眠時無呼吸
中枢性睡眠時無呼吸は、脳が呼吸筋に適切な信号を送らないことで呼吸が一時的に停止するタイプの睡眠時無呼吸症候群です。このタイプは比較的珍しいものです。主な原因としては、以下のような脳や神経の疾患が挙げられます。
- 脳梗塞や脳出血、脳腫瘍などの脳疾患
- パーキンソン病などの神経変性疾患
また、心臓のトラブルも関係しており、特に心不全の患者様では「チェーンストークス呼吸」と呼ばれる特徴的な呼吸パターンが見られ、これが中枢性無呼吸のリスクを高めます。
さらに、薬物や鎮静剤の使用も脳に影響を与え、中枢性睡眠時無呼吸を引き起こすことがあります。
睡眠時無呼吸症候群の検査
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合、以下のステップで検査と診断が行われます。
問診・睡眠尺度評価(ESS)
まず、いびきや無呼吸の症状、自覚症状、過去の病歴などについてお伺いします。さらに、睡眠尺度評価(ESS)という質問表を使って、病的な眠気があるかどうかをチェックします。ただし、睡眠時無呼吸症候群の患者様の中には、眠気を感じない方も少なくありません。そのため、自覚症状がなくても、循環器疾患をお持ちの方などでは、睡眠時無呼吸の可能性を考慮して検査を行うことがあります。
スクリーニング検査
睡眠時無呼吸症候群かどうか、または他の病気が関係しているかを判断するため、パルスオキシメーターを使用します。指先にセンサーを装着し、血液中の酸素レベルや脈拍数を測定することで、無呼吸による酸素不足の状態を確認します。この検査はご自宅で行うことができ、睡眠中の酸素状態を計測できます。
簡易無呼吸検査
こちらの検査では、指や呼吸にセンサーを装着して、睡眠中の血中酸素量や呼吸状態を測定します。これにより、無呼吸や低呼吸の頻度(AHI)や酸素不足の状態を評価できます。当院から機器などをお貸しし、自宅で実施していただきます。簡便に、普段の睡眠状態に近い状況で検査が行えます。
ポリソムノグラフィー(PSG)検査
これは、脳波・筋電図・心電図・呼吸・血液中の酸素などの生体信号を計測する、睡眠時無呼吸症候群の検査の中で最も精密な方法です。この検査では、無呼吸や低呼吸の頻度、SASの種類(閉塞性・中枢性)、酸素の低下状態などを詳細に把握できます。また、睡眠の質(深さ・覚醒の有無)や不整脈、その他の睡眠障害の有無も確認することができます。
この検査は、複数のセンサーを体に装着するため、専門の医療機関で入院して受ける必要があります。全睡眠時間を通して計測でき、無呼吸の状態をより正確に把握することができます。
睡眠時無呼吸症候群の治療
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、生活習慣と深い関わりのある疾患です。当院では、専門的な治療機器だけに頼らず、生活習慣の改善を重視した診療を行っています。
当院のアプローチ
生活習慣の見直し
肥満や高血圧、糖尿病など、生活習慣病がSASのリスク要因となることがあります。当院では、患者様一人ひとりに合わせた体重管理や食生活の見直しをサポートし、症状の改善を目指します。
簡易検査の実施
 自宅で行える簡易検査を提供し、無呼吸の有無や重症度を確認します。検査結果に基づき、最適な治療方法をご提案します。
自宅で行える簡易検査を提供し、無呼吸の有無や重症度を確認します。検査結果に基づき、最適な治療方法をご提案します。
持続陽圧呼吸療法(CPAP)
 中等度以上の症状には、CPAP療法をご案内しています。CPAPは、睡眠中に気道を広げる空気を送り込むことで、無呼吸を予防し、日中の眠気や疲労感を軽減します。
中等度以上の症状には、CPAP療法をご案内しています。CPAPは、睡眠中に気道を広げる空気を送り込むことで、無呼吸を予防し、日中の眠気や疲労感を軽減します。
睡眠時無呼吸症候群に
関するよくある質問
睡眠時無呼吸症候群はどんな人がなりやすいですか?
睡眠時無呼吸症候群は、上気道が閉塞されることで呼吸が浅くなったり止まったりする疾患です。通常、肥満気味の中年男性に多く見られますが、子供や女性、痩せ型の方でも発症するケースは決して少なくありません。首が太く短い方、舌や舌の付け根が大きい方、下顎が小さい方、顎が後退している方など、気道が狭くなりやすい体質の方は発症リスクが高い特徴があります。
睡眠時に無呼吸にならない方法はある?
横向きで寝ることをお勧めします。確かに「横向きで寝るだけで良いのか?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、横向きになって就寝すると、重力の影響が少なくなるため、舌の付け根が喉の方へ落ち込むのを予防しやすくなります。気道が狭くなるのを予防し、呼吸がスムーズに行えるため、睡眠時無呼吸症候群の予防効果に期待できます。
横向き寝の効果をより実感するために、抱き枕を活用することもお勧めできます。抱き枕を抱えることで寝相が安定し、よりリラックスして眠りやすくなります。
いびきが大きいのは病気ですか?
いびきが大きいと感じたり、ご家族やパートナーから指摘を受けたりすることがあるかもしれません。それが「睡眠時無呼吸症候群」の兆候である可能性があります。中でも特に多いのは、上気道の閉塞による「閉塞性睡眠時無呼吸症」です。国内での患者数はおよそ900万人以上と推定されております。しかし、自覚症状が軽微であるため、実際に治療を受けている方は50万人にも満たないと指摘されています。近年では、この疾患が高血圧、心筋梗塞、糖尿病などを悪化する要因になると判明されるようになりました。
睡眠時無呼吸症候群では、夜中に起こした方が良いですか?
睡眠時無呼吸症候群の場合、基本的に無理に起こす必要はありません。しかし、呼吸が長時間止まっている、または息苦しそうな様子が見られる場合は、一度ご相談ください。
急にいびきをかくようになったのですが、睡眠時無呼吸症候群が関係していますか?
可能性はありますが、一時的な要因でいびきをかくことも多いです。SASの場合、いびきが大きいだけでなく、途中でいびきが止まる無呼吸や日中の強い眠気が見られることが特徴です。一方、疲労、鼻づまり、アルコール摂取なども突然いびきをかく原因になり得ます。これらが原因の場合、生活習慣を見直すことで改善することが多いです。
いびきが頻繁であったり、症状が続く場合は、睡眠の問題の可能性があるため、お早めにご相談ください。